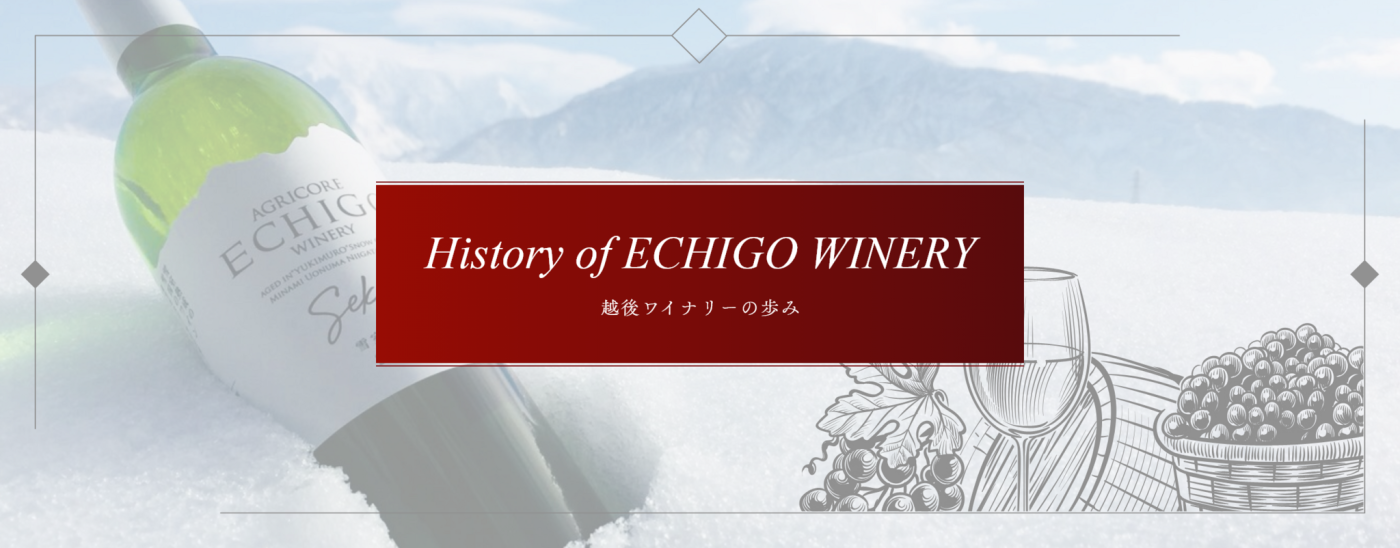
越後ワイナリーの歩み
第1章
― 雪国の挑戦
越後ワイナリーのある新潟県南魚沼市は日本でも有数の寒冷地であり、冬の寒さと多くの雪が降る地域です。この厳しい気候が、一般的にワイン用のブドウを育てるには不適切だとされていました。多くの人々がこの地域でワイン作りを試みなかった理由がここにあります。しかし、越後ワイナリーの創業者たちは、この土地の特性を逆手に取ることで可能性を感じました。
特に、ワインの可能性を信じていた創業者の種村は、雪国ならではの自然条件を活かしたワイン作りができるのではないかと考えました。彼は新潟の気候が持つ特徴をワインの風味にどう活かせるかを模索し始めます。寒冷地特有の収穫のタイミングやブドウの栽培方法に着目したのです。この地域が持つ特性を前向きに捉え、他の地域では味わえない独自のワインを作りたいという強い思いが、越後ワイナリー設立の原動力となりました。
また、種村はワイン造りに必要な技術を学ぶために国内外を見学し、実際にワイン産業の先進地を訪れて多くの知識と経験を得ることになります。その結果、新潟の土地でも可能なワイン造りの方法を考案し、準備が整った段階で本格的にワイン用ブドウの栽培を始めます。
特に、ワインの可能性を信じていた創業者の種村は、雪国ならではの自然条件を活かしたワイン作りができるのではないかと考えました。彼は新潟の気候が持つ特徴をワインの風味にどう活かせるかを模索し始めます。寒冷地特有の収穫のタイミングやブドウの栽培方法に着目したのです。この地域が持つ特性を前向きに捉え、他の地域では味わえない独自のワインを作りたいという強い思いが、越後ワイナリー設立の原動力となりました。
また、種村はワイン造りに必要な技術を学ぶために国内外を見学し、実際にワイン産業の先進地を訪れて多くの知識と経験を得ることになります。その結果、新潟の土地でも可能なワイン造りの方法を考案し、準備が整った段階で本格的にワイン用ブドウの栽培を始めます。
第2章

― 土地とブドウの研究
新潟という雪国の厳しい気候で、どのブドウが育つかを見極めることは最初の大きな課題でした。ワインに適したブドウ品種を選ぶことは、ワインの品質に直結するため、非常に重要な部分です。
種村たちは、気候に合ったブドウ品種を選ぶために、まず温暖な地域のぶどう栽培に関する知識を集めました。その結果、寒冷地でも育つ可能性が高い品種を選ぶことができました。「シャルドネ」や「メルロー」など、比較的寒さに強い品種を選び、栽培方法を調整しました。しかし、試行錯誤の中で、最初は予想以上の難しさで失敗が続きました。雪国では、ぶどうの栽培には特別な工夫が必要であり、特に霜や雪害のリスクが問題となりました。
そのため、越後ワイナリーは特に気候に適した栽培方法を開発しました。ぶどうの苗を雪で覆うことで霜を防ぎ、寒風から守る工夫をしたり、雪解け水を利用して土壌の栄養分を増やしたりするなど、地域特有の環境を利用して栽培を成功に導く方法を探しました。新潟の冷涼な気候は、逆にブドウに独特の風味を与えるため、種村たちはその特性を十分に活用することに注力しました。
地元の人々は、雪国特有の作物栽培に対する豊かな経験を持っており、彼らと協力することでさらに栽培技術を高めることができました。地域の人々との連携は、越後ワイナリーにとって成功への大きな要因となります。
種村たちは、気候に合ったブドウ品種を選ぶために、まず温暖な地域のぶどう栽培に関する知識を集めました。その結果、寒冷地でも育つ可能性が高い品種を選ぶことができました。「シャルドネ」や「メルロー」など、比較的寒さに強い品種を選び、栽培方法を調整しました。しかし、試行錯誤の中で、最初は予想以上の難しさで失敗が続きました。雪国では、ぶどうの栽培には特別な工夫が必要であり、特に霜や雪害のリスクが問題となりました。
そのため、越後ワイナリーは特に気候に適した栽培方法を開発しました。ぶどうの苗を雪で覆うことで霜を防ぎ、寒風から守る工夫をしたり、雪解け水を利用して土壌の栄養分を増やしたりするなど、地域特有の環境を利用して栽培を成功に導く方法を探しました。新潟の冷涼な気候は、逆にブドウに独特の風味を与えるため、種村たちはその特性を十分に活用することに注力しました。
地元の人々は、雪国特有の作物栽培に対する豊かな経験を持っており、彼らと協力することでさらに栽培技術を高めることができました。地域の人々との連携は、越後ワイナリーにとって成功への大きな要因となります。
第3章
― 雪国の特性を活かす
新潟の厳しい気候条件を逆手に取ることで、他の産地とは異なる特別なワインを生み出そうという試みを実施しました。
一つの特徴的なポイントは、雪解け水の利用です。新潟の雪解け水は非常に清らかでミネラルを豊富に含んでおり、これがぶどうに良い影響を与えると考えられました。
雪国の寒冷な気候は、ぶどうの成長を遅らせるため、ぶどうが成熟するまでの時間が長く、その分味わいが深くなるという特徴を持っています。この特性を活かすために、越後ワイナリーでは、ブドウの収穫タイミングに特に注意を払い、他の産地では得られない深い風味を持つワインを作ることができました。雪国特有の冷涼な気候が、ワインに繊細な酸味や豊かな香りをもたらし、越後ワイナリーの特徴的な味わいを形成したのです。
また、越後ワイナリーは、地域の自然環境を保護するための努力も重視しました。ぶどう栽培の過程で農薬の使用を極力減らし、環境に優しい方法で栽培を行い、地域の自然と調和することを目指しました。これにより、地域社会や消費者からの信頼を得ることができました。
一つの特徴的なポイントは、雪解け水の利用です。新潟の雪解け水は非常に清らかでミネラルを豊富に含んでおり、これがぶどうに良い影響を与えると考えられました。
雪国の寒冷な気候は、ぶどうの成長を遅らせるため、ぶどうが成熟するまでの時間が長く、その分味わいが深くなるという特徴を持っています。この特性を活かすために、越後ワイナリーでは、ブドウの収穫タイミングに特に注意を払い、他の産地では得られない深い風味を持つワインを作ることができました。雪国特有の冷涼な気候が、ワインに繊細な酸味や豊かな香りをもたらし、越後ワイナリーの特徴的な味わいを形成したのです。
また、越後ワイナリーは、地域の自然環境を保護するための努力も重視しました。ぶどう栽培の過程で農薬の使用を極力減らし、環境に優しい方法で栽培を行い、地域の自然と調和することを目指しました。これにより、地域社会や消費者からの信頼を得ることができました。
第4章

― 初めての収穫とワイン作り
新潟の厳しい気候条件の中で、ようやくぶどうの栽培が軌道に乗り始め、収穫の時期が訪れます。しかし、初めての収穫には予想以上の難しさと課題が待ち受けていました。
越後ワイナリーが選んだワイン用ぶどうの品種は、寒冷地でも育つものが中心であり、特に冷涼な気候の中で熟成が遅れることから、収穫のタイミングには非常に神経を使いました。収穫時期が遅くなると、気温の低さや霜害のリスクが高まるため、タイミングを逃すことがないように注意深く観察を続けました。収穫の前に数回の気象予測を行い、最適なタイミングを見計らって収穫に挑みます。
初めての収穫は、想像以上に少量でした。最初に収穫したぶどうの量は少なかったため、そのすべてをワインに加工することができましたが、少ないながらも初めて手にしたワイン用のぶどうの味は、他の地域とは異なる特徴を持っていました。そのため、越後ワイナリーのチームは、この収穫が将来の大きな一歩となることを確信し、ワイン作りを続ける決意を新たにしました。
収穫後、ワインを作るための醸造が始まります。初めてのワイン作りは予想以上に難しく、発酵のコントロールや温度管理、酸化を防ぐための処理方法に工夫が必要でした。特に、発酵が進むスピードや味のバランスに苦労することになりました。しかし、ワイン作りの過程を通して、技術的な課題を解決し、ブドウの持ち味を最大限に引き出す方法を模索していきます。
ワインの仕込みを重ねる中で、初めての成功と失敗の両方を経験しながら、少しずつ技術が確立されていきました。特に、地元の気候や土壌に適した醸造方法を見つけることが、越後ワイナリーにとって重要な課題でした。種村たちは多くの実験を重ね、ぶどうの品種や発酵方法、熟成方法を微調整して、最終的に独自の風味を持ったワインを作り上げることに成功します。
越後ワイナリーが選んだワイン用ぶどうの品種は、寒冷地でも育つものが中心であり、特に冷涼な気候の中で熟成が遅れることから、収穫のタイミングには非常に神経を使いました。収穫時期が遅くなると、気温の低さや霜害のリスクが高まるため、タイミングを逃すことがないように注意深く観察を続けました。収穫の前に数回の気象予測を行い、最適なタイミングを見計らって収穫に挑みます。
初めての収穫は、想像以上に少量でした。最初に収穫したぶどうの量は少なかったため、そのすべてをワインに加工することができましたが、少ないながらも初めて手にしたワイン用のぶどうの味は、他の地域とは異なる特徴を持っていました。そのため、越後ワイナリーのチームは、この収穫が将来の大きな一歩となることを確信し、ワイン作りを続ける決意を新たにしました。
収穫後、ワインを作るための醸造が始まります。初めてのワイン作りは予想以上に難しく、発酵のコントロールや温度管理、酸化を防ぐための処理方法に工夫が必要でした。特に、発酵が進むスピードや味のバランスに苦労することになりました。しかし、ワイン作りの過程を通して、技術的な課題を解決し、ブドウの持ち味を最大限に引き出す方法を模索していきます。
ワインの仕込みを重ねる中で、初めての成功と失敗の両方を経験しながら、少しずつ技術が確立されていきました。特に、地元の気候や土壌に適した醸造方法を見つけることが、越後ワイナリーにとって重要な課題でした。種村たちは多くの実験を重ね、ぶどうの品種や発酵方法、熟成方法を微調整して、最終的に独自の風味を持ったワインを作り上げることに成功します。
第5章

― 地域との連携
越後ワイナリーの成功には、単にワイン作りの技術だけでなく、地域との強い絆が不可欠でした。
新潟のような寒冷地でワイン用のブドウを育てるには、農家の協力が重要です。越後ワイナリーは、ワイン用ぶどうの栽培に関して多くの農家と連携し、その技術を共有し合いました。特に、雪国での栽培技術は独特であり、農家たちの長年の経験が大きな助けとなりました。彼らは、ぶどう栽培に必要な知識や技術を提供し、越後ワイナリーはその協力を通じて栽培方法を改良していきました。地域の農家たちにとっても、新しい収入源を得るチャンスとなり、協力関係が強化されていきます。
また、越後ワイナリーは地域経済に対しても大きな貢献をしています。ワイン作りが進むことで、地元の雇用が増え、観光業にも好影響を与えるようになりました。地域の特産品としてワインが注目され、地元の飲食店や観光地での提供が進みました。このように、越後ワイナリーは単なるワイン生産の場ではなく、地域全体の活性化に寄与する存在へと成長していきました。
さらに、越後ワイナリーは地域の文化や伝統とも深く結びつくことを目指しました。地元の文化を尊重し、その文化に根ざしたワイン作りを行うことで、地域の人々の誇りとなり、ワイン自体も地域のアイデンティティの一部として認識されるようになりました。地元の農家や住民との信頼関係を築き、ワイン作りが地域の特色を活かす手段となるよう努力しました。
地域社会との協力がなければ、越後ワイナリーの成功は成し得ませんでした。越後ワイナリーは地域との連携を大切にし、共に成長する道を選んだのです。
新潟のような寒冷地でワイン用のブドウを育てるには、農家の協力が重要です。越後ワイナリーは、ワイン用ぶどうの栽培に関して多くの農家と連携し、その技術を共有し合いました。特に、雪国での栽培技術は独特であり、農家たちの長年の経験が大きな助けとなりました。彼らは、ぶどう栽培に必要な知識や技術を提供し、越後ワイナリーはその協力を通じて栽培方法を改良していきました。地域の農家たちにとっても、新しい収入源を得るチャンスとなり、協力関係が強化されていきます。
また、越後ワイナリーは地域経済に対しても大きな貢献をしています。ワイン作りが進むことで、地元の雇用が増え、観光業にも好影響を与えるようになりました。地域の特産品としてワインが注目され、地元の飲食店や観光地での提供が進みました。このように、越後ワイナリーは単なるワイン生産の場ではなく、地域全体の活性化に寄与する存在へと成長していきました。
さらに、越後ワイナリーは地域の文化や伝統とも深く結びつくことを目指しました。地元の文化を尊重し、その文化に根ざしたワイン作りを行うことで、地域の人々の誇りとなり、ワイン自体も地域のアイデンティティの一部として認識されるようになりました。地元の農家や住民との信頼関係を築き、ワイン作りが地域の特色を活かす手段となるよう努力しました。
地域社会との協力がなければ、越後ワイナリーの成功は成し得ませんでした。越後ワイナリーは地域との連携を大切にし、共に成長する道を選んだのです。
第6章

― 苦難と試練
ワイン作りは単なる技術や情熱だけでは成功しないという現実に直面し、越後ワイナリーは多くの障害を乗り越えてきました。
まず、経営的な課題に直面します。最初の数年間は、収益が上がらず、運営資金を確保するために多くの努力を強いられました。ワイン作りには長期間の熟成期間が必要であり、その間は費用がかさむ一方で収入は見込めません。また、収穫量が安定しないことも経営の難しさを加速させました。それでも越後ワイナリーは地域の支援を受けながら、なんとか乗り越えていきます。
さらに、自然災害や天候の影響が大きな試練となります。特に新潟県では豪雪や大雨などの自然災害が発生することがあり、これらがぶどう栽培に与える影響は計り知れません。雪害や霜害がブドウの収穫に大きなリスクをもたらし、最悪の状況が続くこともありました。しかし、越後ワイナリーはこれらの困難に対して冷静に対応し、災害後の復旧活動や収穫への影響を最小限に抑えるための戦略を練り直しました。
まず、経営的な課題に直面します。最初の数年間は、収益が上がらず、運営資金を確保するために多くの努力を強いられました。ワイン作りには長期間の熟成期間が必要であり、その間は費用がかさむ一方で収入は見込めません。また、収穫量が安定しないことも経営の難しさを加速させました。それでも越後ワイナリーは地域の支援を受けながら、なんとか乗り越えていきます。
さらに、自然災害や天候の影響が大きな試練となります。特に新潟県では豪雪や大雨などの自然災害が発生することがあり、これらがぶどう栽培に与える影響は計り知れません。雪害や霜害がブドウの収穫に大きなリスクをもたらし、最悪の状況が続くこともありました。しかし、越後ワイナリーはこれらの困難に対して冷静に対応し、災害後の復旧活動や収穫への影響を最小限に抑えるための戦略を練り直しました。
第7章
― 成功と未来
ワインの品質が向上し、地域の経済にも貢献する存在となった越後ワイナリーは、地元の特産品として確固たる地位を築くことができました。
さらに、越後ワイナリーは、未来に向けてさらに新しい挑戦を続けています。これからのワイン作りでは、さらに品質を高めるとともに、持続可能な農業と環境保護を両立させるための努力が必要です。また、新たな市場の開拓や、他の地域との協力を通じて、越後ワイナリーの名声をさらに広げるための計画が描かれています。
地域社会と共に歩み続ける越後ワイナリーの未来には、多くの可能性が広がっています。
さらに、越後ワイナリーは、未来に向けてさらに新しい挑戦を続けています。これからのワイン作りでは、さらに品質を高めるとともに、持続可能な農業と環境保護を両立させるための努力が必要です。また、新たな市場の開拓や、他の地域との協力を通じて、越後ワイナリーの名声をさらに広げるための計画が描かれています。
地域社会と共に歩み続ける越後ワイナリーの未来には、多くの可能性が広がっています。
会長紹介

会長 種村 芳正
1928年生まれ、新潟県南魚沼出身。地域活性化を目指しワイン造りに挑戦する。1973年、葡萄栽培技術を学ぶためフランスのボルドーへと渡る。
ボルドーで「品質こそ全て」の信念を貫く醸造家達に出会い、良品質なワイン造りに影響を受ける。
帰国後、創業の準備を進め、わずか5人で前身の「越後ワイン」を1975年10月に立ち上げる。観光地であるということもあり、良質なワインは土産物としても人気がある。
従業員は種村のことを「とてもフットワークが軽く、エネルギーに満ち溢れている人」と話す。年を重ねた今でも醸造家と共に畑に出て作業を行う。誰よりもワインが好きで、毎日ワインを飲む事が元気で生活できる源のようだ。



